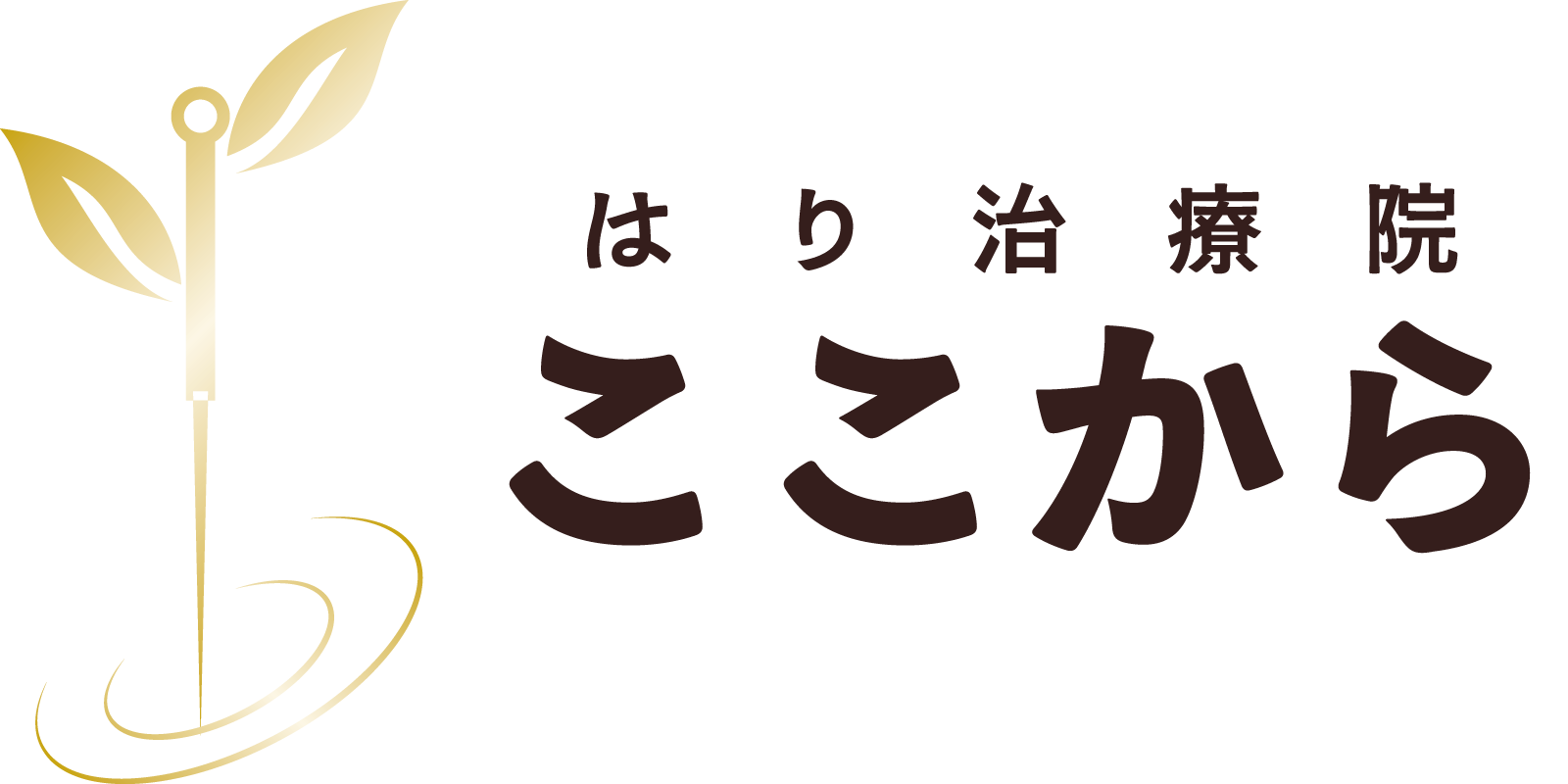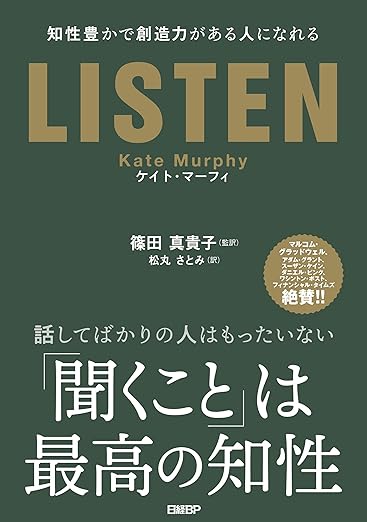本書は聴くことを賛美する本であり、また文化として「聴く」力が失われつつあるような現状を憂う本でもあります。
Kate Murphy
ケイト・マーフィー著『LISTEN』を読みました。
ニューヨーク・タイムズなどで活躍するジャーナリストが
これまで数え切れない人にインタビューをしてきた経験から
「聴くこと」の大切さを書いた本です。
読んでいくと、
人の話を真剣に聴いたのはいつだろう?
誰かに真剣に自分の話を良いてもらったのはいつだろう?
と考えてしまいました。
自分の心ばかり見つめる現代で、
他者の声を聴くことがなくなっていると
著者のケイトさんは伝えてくれています。
集中力が8秒しか持たない時代に
「人の集中力の平均時間が12秒から8秒まで低下している」
という記述があり、びっくりしました。
アテンション・エコノミーというそうですが、
SNS企業は人々の関心や注目度合いによって経済価値が決まる。
僕が注意力散漫になるほど、
企業が儲かる仕組みなのです(笑)
人は家にいるときでも、
1時間に平均21回もデバイスを切り替えているそうです。
パソコンを見て、ページ読み込み中にスマホをチェックして。
思い当たる節があります。。。
また、ウェブサイトの読み込みが3秒を超えると苛立ってページを離れる。
さらに、音声や動画を倍速で聞き続けると、
普通の速度で会話をするときに
相手の言葉に集中することが難しくなるそうです。
速さに慣れすぎると、
声のニュアンスや感情の揺らぎを感じ取る力まで失われてしまうと。
自分も同じだった
恥ずかしながら、自分も思い当たる節しかありません。。。
トイレにまでスマホを持ち込み、
奥さんに注意されたこともあります(^_^;)
ひとりの時はご飯やお風呂の時間もつい動画を再生して、
長い動画だと倍速視聴が当たり前に。
2倍くらいの音声で聞いていると、
通常速度の動画がまどろっこしく感じてしまうんですよね💦
それが効率的だと思っていましたが、
振り返ればただ「落ち着けない自分」をごまかしていただけでした。

治療の現場で感じたこと
怖いのは、こうした習慣が治療の現場にも影響するということです。
患者さんの声のトーンや会話の間合いは、
体調や心の状態を知る大切なサイン。
でも、自分が速さや刺激ばかりを追いかけていると、
その微妙な変化に気づく感度が鈍ってしまう。
本書を読みながら、
これは自分自身の課題であり、
治療の質にも直結することだ
とハッとしました。
「自分のきほん」に立ち返る
以前のブログで「自分のきほんを作る」という話を書きました。
「相手の話を遮らず、横取りせず、よく聴く」
ということをきほんのひとつにしましたが、
きほんがまだまだできていないことを本書が教えてくれました(笑)
『LISTEN』は、「きほんを修正するヒント」になったのです。
まずは小さな実験から
とりあえずの対策として、
スマートフォンからSNSアプリを削除しました(笑)
集中力が一気に戻ったわけではありませんが、
失っていた時間に気がつくようになりました。
そして、基本は倍速再生はしないようにしています。
これも不思議ですが、
常に倍速ではない通常再生で聞いていれば
まどろっこしさをあまり感じなくなっています。
発信することの重要性が叫ばれる現代で、
今一度「聴くこと」の役割を学べたことは
とても為になりました。
気になる方はぜひ読んでみて下さい!